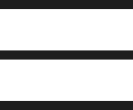美容師にとって「手荒れ」は避けて通れない大きな悩みです。
美容師本人はもちろん、美容学生やサロン経営者にとっても、手荒れの原因や効果的な対策を知っておくことは重要でしょう。
実際、多くの美容師が何らかの手荒れを経験しており、ヘアカラーによるアレルギーに悩む美容師は例外なく手荒れが見られるとも言われています。
本記事では、美容師の手荒れについて「なぜ起こるのか」という原因から、今日から実践できる予防策、皮膚科での治療や労災申請のポイントまで網羅的に解説します。
適切な知識を身につけて、大切な手を守りながら美容の仕事を続けられるようにしましょう。
手荒れの原因と症状:なぜ美容師は手が荒れやすい?

美容師の手荒れ(いわゆる手湿疹・主婦湿疹)は、物理的・化学的刺激による皮膚バリア機能の低下が主な原因です。
具体的には、美容室での日常業務における以下のような要因が重なり、手指の潤いを奪って炎症を引き起こします。
- 頻繁なシャンプーやお湯による洗髪作業:皮膚が長時間水やお湯に触れると、表面の皮脂が洗い流されてしまいます。
特に美容師はお客様ごとに手を濡らす必要があり、一日に何度も手洗いや洗髪を繰り返すため、皮脂による保護膜がほぼ常にゼロの状態になります。
シャンプー剤に含まれる界面活性剤も皮脂を奪い、肌を乾燥させてしまいます。
結果として角質層のバリアが壊れ、外部刺激に対する抵抗力が低下します。 - カラー剤・パーマ液など薬剤による刺激やアレルギー:ヘアカラーやパーマで使用する薬剤は皮膚にとって刺激が強く、繰り返し触れることで炎症やかぶれを起こしやすくなります。
特にカラー剤に含まれるパラフェニレンジアミン(パラトルエンジアミン)や、パーマ液のチオグリコール酸アンモニウムといった成分はアレルギー性接触皮膚炎の原因物質として知られ、これらが原因で皮膚障害を発症するケースが報告されています。
一度アレルギーを発症すると、微量の曝露でも激しいかぶれを起こすようになるため厄介です。
なお、美容師が仕事で起こす皮膚炎は昔から頻発していますが、原因物質の特定が難しく労災認定が少なかった経緯があります(1978~2016年度で128件に留まる)。
しかし近年は上記のような特定物質が職業病の原因として公式に認められ、より対策が重視されるようになっています。 - ドライヤーの熱風やタオルドライ:シャンプー後のブロー作業で浴びる熱風や、タオルでゴシゴシと手を拭く動作も、実は手肌の水分を奪い乾燥を進める要因です。
濡れた肌に熱風を当てると瞬時に水分が蒸発し、さらに乾燥が悪化します。
以上のような「水仕事+薬剤+乾燥」の繰り返しにより、美容師の手肌は角質層の潤い保持機能が著しく低下します。
その結果、最初は軽いカサつき程度だった手荒れが次第にひび割れや炎症を伴う湿疹へと進行しやすくなるのです。
さらにバリア機能の低下した皮膚ではアレルゲンの侵入を許しやすくなるため、手荒れがある状態自体が後々アレルギー性皮膚炎を引き起こす下地になってしまいます。
例えばカラー剤でかぶれを起こす美容師は、その下地に慢性的な手荒れが存在しているケースがほとんどです。
症状の現れ方は段階的で、適切に対処しないと悪化していきます。
初期には手のひらや指先が少しガサガサする程度ですが、進行すると皮膚が硬くゴワついてきて、ひび割れや出血が見られることもあります。
かゆみも強くなり、就寝中につい掻きむしってしまい、朝起きたら手が血まみれになっていた…という笑えない事態に陥ることもあります。
重症化した手荒れでは、角化した分厚い皮膚が剥け落ちはじめ、真皮まで露出することで手指が赤く腫れて痛みと激しいかゆみを伴います。
指を曲げるのも辛くなり、水疱(みずぶくれ)ができては潰れ、中から黄色い液体(リンパ液や膿)がにじみ出ることもあります。
こうなると二次感染(細菌感染)を起こして患部が熱を持ち腫れるリスクも高まり、ますます治りにくくなってしまいます。
「腕までかゆみや発疹が広がった」「指から膿が出ている」という状態は明らかに重症と言えますので、早急に皮膚科を受診して適切な治療を受けることが必要です。
手荒れを予防・改善する効果的な対策
「手荒れは予防が何より大事」――症状が軽いうちにケアすることで、重症化を防ぎ仕事への支障も最小限に抑えられます。
ここでは、美容師が現場で実践できる手荒れ対策を具体的に紹介します。
今日からできることばかりですので、ぜひ取り入れてみてください。
1. 業務時の手袋着用を徹底する

美容師の手荒れ予防で最も重要なのは「手袋」を活用することです。
シャンプー時はもちろん、カラーやパーマの塗布・洗い流し、掃除や洗濯などすべての作業で手袋を着用する習慣をつけましょう。
手袋をすることで有害な薬液や水分が直接肌に触れるのを防ぎ、皮脂の流出や刺激物の浸入を大幅に減らすことができます。
手袋は使い回しせず可能な限り使い捨てのものを使うのがおすすめです。
繰り返し使った手袋にはシャンプー剤や薬剤が付着・蓄積しており、裏側にそれらが残っていると逆効果になります。
また、手袋自体の素材も重要です。
一般的なビニール手袋やポリ手袋でも一定の効果はありますが、ヘアカラー剤の染料成分が浸透しにくい「ニトリル製」の手袋が望ましいとされています。
特にゴムアレルギー(ラテックスアレルギー)の心配がある場合は、天然ゴム不使用で加硫促進剤(ゴム手袋の製造過程で用いられる化学物質)を含まないニトリル手袋を選ぶと安心です。
手首までしっかりカバーできる長めの手袋であればなお良いでしょう。
インナー手袋の活用
手袋の中が蒸れてしまい長時間つけていられない…という場合は、綿のインナー手袋を併用すると快適です。
綿手袋が汗を吸収しムレを軽減してくれます。
こまめに取り替えて清潔に保ちましょう。
なお、中には「お客様に失礼では?」「感覚が鈍るから…」といった理由で手袋を敬遠する美容師さんもいます。
しかし健康あっての美容師業です。
お客様には手荒れ対策のため手袋を着用している旨を説明し、プロとしてセルフケアに努めている姿勢を示した方が結果的に信頼にもつながるでしょう。
2. こまめな保湿と適切なスキンケア

こまめに保湿することは手荒れ対策の基本です。
「忙しくてハンドクリームを塗る暇がない」「ベタつくから仕事中は避けたい」という声もありますが、最近は美容師向けにベタつきが少なくサッと馴染むタイプのハンドクリームも市販されています。
仕事の合間やシャンプー後などにこまめに塗り直し、常に肌に潤いを補給しましょう。
ハンドクリームはすぐ手に取れる場所に置いておくかポケットに入れて携帯し、忘れず塗れる工夫をすることも大切です。
また、手の洗い方や乾かし方にも注意が必要です。
薬剤が手に付着したまま放置すると炎症の原因になるため、カラー剤やパーマ液を扱った後やお客様のシャンプーが終わった後などは、できるだけ早く低刺激性の石けんできちんと手を洗い落としましょう。
その際ゴシゴシ洗いすぎると逆効果なので、泡で優しく洗って十分にすすぎます。
洗った後は清潔なタオルで水分をしっかり拭き取ることも忘れないでください。
濡れたままにしておくと蒸発時に肌が乾燥しますし、手袋の中で蒸れて肌トラブルを悪化させる恐れもあります。
傷口がある場合は、その部分をカバーして保護することも大切です。
指先のあかぎれやひび割れには絆創膏やキズパワーパッドなどの保護剤を上手に使い、刺激や水が直接入らないようにしましょう。
特に近年人気のハイドロコロイド素材の保護パッドは患部の治癒を早める効果も期待できます。
関節部分など貼りにくい箇所用に工夫された形状のものも市販されていますので活用してください。
さらに症状や肌質に合わせて、場合によっては市販薬の使用や漢方の併用も検討します。
かゆみが強いときは市販のかゆみ止め外用薬(非ステロイド系のクリームなど)を塗ったり、内服抗ヒスタミン薬を服用するのも一つの方法です。
炎症がひどいときは市販の弱めのステロイド軟膏(例えばプレドニゾロンやデキサメタゾン配合のもの)を短期間使うことで早く症状を沈静化できる場合があります。
ただしステロイドは強さや使い方を誤ると副作用のリスクもあるため、自己判断が不安な場合は皮膚科で相談して処方してもらいましょう。
漢方薬では、慢性的な手湿疹に十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)や黄連解毒湯(おうれんげどくとう)を用いるケースがあります。
これらは体の内側から炎症体質を改善するとされ、市販もされていますが、専門医の指導の下で服用すると安心です。
3. 食事・サプリメントで内側から肌ケア

手荒れ対策は外側からのケアだけでなく、体の内側からのケアも大切です。
肌の新陳代謝を促しバリア機能を高めるために、以下のような栄養素を積極的に摂取するとよいでしょう。
| 栄養素・成分 | 働きや効果の例 | 多く含む食品の例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 健康な皮膚をつくる材料になる | 魚、肉、卵、大豆食品など |
| ビタミン類(A・B群・C・Eなど) | 肌の新陳代謝を助け、荒れた肌の回復を促す(ビタミンAは皮膚粘膜の健康維持、Cはコラーゲン合成を促進 etc.) | 緑黄色野菜、フルーツ、レバー、ナッツ類など |
| 亜鉛 | 傷の治りを早める、皮膚の再生に必要な酵素を活性化する | 牡蠣、魚介、肉、卵、乳製品 |
| 鉄分 | 肌細胞の代謝に必要 ビタミンCとともに摂るとコラーゲン生成を助ける | 赤身の肉、レバー、ほうれん草、貝類 |
| オメガ3系脂肪酸 (α-リノレン酸等) | 抗炎症作用があり、皮膚のバリア機能維持に役立つ | エゴマ油、アマニ油、青魚(EPA/DHA) |
| セラミド | 角質細胞間脂質の主要成分 肌の水分保持・バリア機能を高める | 大豆、米、乳製品、こんにゃく芋 など(※サプリや食品で補う) |
普段の食事でバランス良く栄養を摂ることが基本ですが、忙しい美容師さんは食生活が乱れがちですよね。
その場合は不足しがちな栄養素をサプリメントで補うのも一つの手です。
たとえば皮膚科で処方されることもあるビオチン(ビタミンB7)は、皮膚や粘膜の健康維持に関与するビタミンで、サプリでも市販されています。
また、近年人気のセラミド配合サプリ(機能性表示食品として「皮膚のバリア機能を高め保湿に役立つ」と表示された商品もあります)を利用してみるのも良いでしょう。
もちろんサプリだけに頼るのではなく、規則正しい食生活と十分な睡眠・休養をとって体調を整えることが、肌のコンディション改善には何より大切です。
4. 薬剤・器具の見直しや仕事環境の工夫

手荒れが慢性化するようであれば、職場で使用する薬剤や器具を見直すことも検討しましょう。
最近では、美容室向けにも低刺激やアレルギーフリーを謳ったシャンプー剤・カラー剤が販売されています。
たとえばジアミン系色素不使用のヘアカラー剤や、手肌に優しい処方のシャンプーなどです。
コストや仕上がりとの兼ね合いもありますが、可能であればサロン全体で導入を検討してみても良いかもしれません。
また、シャンプー台の水温設定を少し下げたり、手袋や保湿クリームのメーカーを変えてみるだけで症状が改善するケースもあります。
職場の同僚や先輩美容師と情報交換しながら、自分に合った環境づくりを模索してみましょう。
仕事のやり方を工夫することも大切です。
例えば、アシスタントのうちはシャンプーやカラー塗布など手荒れしやすい作業が多いですが、できる範囲でローテーションを組んでずっと同じ作業が続かないようにする、薬剤塗布の際は手より道具(ハケやコーム)を使うようにする、といった工夫で手への負担を減らすことができます。
サロン全体で手荒れ防止に取り組むことが、スタッフの離職防止にもつながるでしょう。
皮膚科を受診すべきケース

上述の対策を講じても手荒れの症状が2週間以上良くならない場合や、明らかに悪化している場合は、我慢せず皮膚科専門医を受診しましょう。
特に下記のような場合は専門的な治療が必要です。
- 亀裂が深く出血や浸出液が止まらない:市販の処置で塞がらないほどのひび割れは感染リスクもあります。
- 掻ゆう(そう痒)が強く眠れない:強いかゆみは炎症がかなり進んでいるサインです。適切な薬で鎮める必要があります。
- 水ぶくれが次々できる:湿疹が急性期にあり、ステロイドなどで炎症を抑えないと悪化する恐れがあります。
- 腫れや膿がある:細菌感染を起こしている可能性が高く、抗生剤の内服や軟膏が必要です。
- 腕や顔など手以外の部位に広がっている:アレルギー反応による可能性があり、専門的な検査・治療が望ましいです。
- 市販薬を使っても改善しない:自己ケアの限界を超えている可能性があります。
皮膚科では、症状に合わせてステロイド外用薬(軟膏やクリーム)や保湿剤(尿素やヘパリン類似物質配合クリーム、ワセリンなど)を処方してもらえます。
炎症をしっかり抑えることで皮膚のバリア機能が回復しやすくなり、結果的に早く治すことができます。
症状が落ち着いてきたら、ステロイドに替えて非ステロイド系の消炎剤や保湿剤のみのケアに移行するといった治療プランを立ててもらえるでしょう。
かゆみが強い場合は抗ヒスタミン薬の内服を併用することもあります。
また、症状や経過によってはパッチテスト(皮膚アレルギー試験)を行い、特定の物質に対するアレルギーの有無を調べてもらえます。
美容師の場合、カラー剤の成分やゴム手袋の成分など職業性のアレルゲンが疑われますので、一度検査しておくと今後の対策に役立ちます。
仮に特定の成分に陽性反応が出た場合、医師から「その成分を含む業務は避けるように」と指導を受けることもあります(これが後述するドクターストップにつながるケースです)。
ドクターストップがかかる場合とその後の選択肢

「ドクターストップ」とは、担当医から「これ以上この仕事を続けるのは健康上困難」と判断され、業務の継続を制限・禁止されることを指します。
美容師の手荒れにおいてドクターストップが下るケースも実際に存在し、手荒れが原因で医師に仕事継続を止められ泣く泣くスタイリストの道を諦めた人もいます。
では、どのような場合にドクターストップとなり、もしそうなったらどんな選択肢があるのでしょうか。
重度の手湿疹で医師の治療を続けても改善せず、むしろ悪化の一途をたどっている場合や、特定の業務に対する明確なアレルギーが判明した場合に、ドクターストップが検討されます。
例えば「パーマ液の成分に強いアレルギー反応を持っており、このまま美容師の仕事を続ける限り完治は難しい」と医師が判断したようなケースです。
この場合、医師から「美容師の業務を一定期間中断するか、完全にやめない限り治らない」と告げられることがあります。
非常に辛い決断ですが、炎症が収まらないまま無理に働き続けると将来的に手が使えないほど後遺症が残る可能性もありますので、医師の判断は尊重すべきです。
ドクターストップがかかった場合の選択肢としては、大きく分けて「休職して治療に専念する」か「美容師自体を退職・転職する」かの二択になります。
ただし、いきなり仕事を失うのは現実的に難しいでしょうから、まずは一定期間の休職や業務内容の変更から検討するのが一般的です。
たとえば数か月間シャンプーや薬剤を扱う業務を休み、その間に治療とリハビリを行って症状の改善を図る、といった対応です。
それでも改善せず医師から「復帰は難しい」と判断された場合は、残念ながら退職も視野に入れざるを得ません。
ドクターストップ後のキャリアとしては、症状が落ち着いてから他業種へ転職する人もいれば、培った技術を活かしてウィッグスタイリストや美容商品販売、講師業など手荒れのリスクが少ない分野へ活路を見出す人もいます。
また、美容師免許を活かせる職種は美容室だけではなく、ブライダルやヘアメイク業界、化粧品会社のビューティーアドバイザーなど様々あります。
「美容師を辞めても人生は続く」ので、自分の健康第一で前向きに次の道を考えてみてください。
幸い手荒れが軽快して再び美容師に復帰できたケースもありますし、逆にドクターストップを機に新たな才能を開花させて活躍している元美容師さんもいます。
何より大事なのは、そこまで手荒れを悪化させないことです。
「将来のためにも我慢しすぎないで」と肝に銘じてください。
少しでもおかしいと感じたら早めに手を休めケアをする、症状が長引くなら皮膚科に行く、といった適切な対処でドクターストップに至る事態はかなり防げるはずです。
手荒れと労災保険:適用条件と申請のポイント

業務が原因で発症した手荒れ(接触皮膚炎)は、条件を満たせば労働災害(業務上疾病)として労災保険の適用を受けられる可能性があります。
美容師の手荒れは典型的な「職業病」の一つですが、その労災認定は決して簡単ではありません。
しかし、近年では美容師のヘアカラー剤やパーマ剤による皮膚疾患も労災認定されやすくなる見通しが報じられるなど、状況は少しずつ改善されています。
労災保険が適用される条件とは
労災保険が適用される条件としてまず大前提になるのは、「その美容師が事業主に雇用されている労働者であること」です。
サロンオーナーやフリーランス(業務委託)で働いている場合、通常の労災保険の補償対象にはなりません。
※フリーランスの場合は労働局認定の特別加入制度に自ら加入していれば労災保険を使える可能性があります。
次に、「手荒れの発症が業務に起因すること」を証明する必要があります。
これが認められれば、たとえ慢性的な皮膚炎であっても労災保険の給付対象となる可能性があります。
具体的には、仕事上の特定の物質や作業が原因で手荒れになったことが客観的に裏付けられるかがポイントです。
例えば「今までほとんど手荒れを起こしたことがなかったのに、新しく導入したカラー剤を使い始めた途端にひどい手湿疹が出るようになった」といったケースでは、新しいカラー剤が原因であることが明らかであり、因果関係の証明が比較的容易です。
このように原因物質が特定できるケースでは労災認定が下りやすくなります。
実際、厚生労働省の有識者検討会でも、先述のパラフェニレンジアミンやチオグリコール酸アンモニウムによる皮膚障害を業務上疾病と認める方向で報告書案がまとめられています。
一方で、因果関係が明確でない場合は認定が難しくなります。
例えば「手荒れ自体は仕事以外の家事(洗剤を使った掃除や炊事)でも起こり得るため、本当に仕事だけが原因と言い切れない」ようなケースです。
美容師の手荒れは日々の積み重ねで徐々に悪化することが多いため、「いつ・どの作業で発症したか」を一箇所に特定しにくく、労災として認められにくい側面があります。
それでも、皮膚科医の診断書に「職業性皮膚炎(美容師の業務によるもの)」と明記してもらう、社内で同じ薬剤による手荒れ患者が他にも発生している事実を示す、などの工夫で認定を勝ち取った例もあります。
労災保険を申請する方法
労災申請の方法は、基本的に雇用主(サロン経営者)が労働基準監督署に提出する形をとります。
会社に労災担当者がいれば相談しましょう。
必要書類は「疾病報告書」や「療養補償給付支給申請書」などで、診断書や病歴の提出も求められます。
もし会社が労災申請に非協力的な場合でも、労働者本人が直接労基署に申請することも可能です。
その際は労働基準監督署に設置されている労災相談窓口に問い合わせると手順を教えてもらえます。
労災と認定されれば、治療にかかった費用は全額労災保険から給付され自己負担ゼロになります(病院では健康保険ではなく労災扱いで計算)。
さらに、仕事を休まざるを得ない場合は休業補償給付として給料の一部(平均賃金の60%+特別支給金20%)が支給されます。
また、手荒れでここまで至るケースは稀ですが、症状が重く後遺障害が残った場合には等級に応じた障害補償給付もあります。
労災保険は労働者の権利ですから、仕事が原因で起きた手荒れに苦しんでいるのであれば泣き寝入りせず、然るべき制度を利用しましょう。
「大げさかな…」と遠慮する必要は全くありません。治療に専念し、また元気に働けるようになるためにも、使える制度はしっかり使ってください。
まとめ
以上、美容師の手荒れについて原因から対策、治療、制度面まで解説しました。
手荒れは放っておくと仕事の質のみならず美容師人生にも影響を及ぼしかねない重要な問題です。
「職業病だから仕方ない」と諦めずに、正しい知識と適切なケアで症状をコントロールしていきましょう。
幸い、業界全体でも手荒れ対策の重要性が認識されつつあり、国や専門機関からガイドブックが出されたり、学校教育で予防法を教えたりする動きも出ています。
自身の努力+周囲の協力で、手荒れに負けない快適な美容師ライフを送れるよう応援しています!